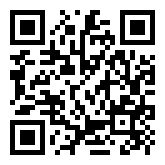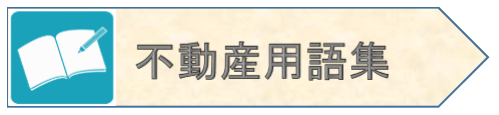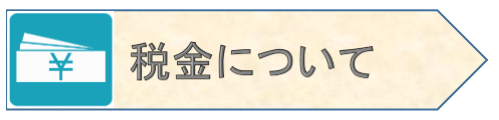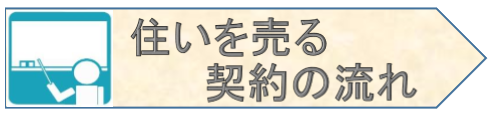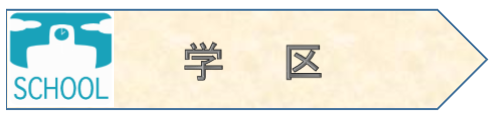不動産用語集
か行
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さ行
住宅ローン
個人に対する住宅資金の融資をいう。
主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある。
融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。
住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。
た行
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。